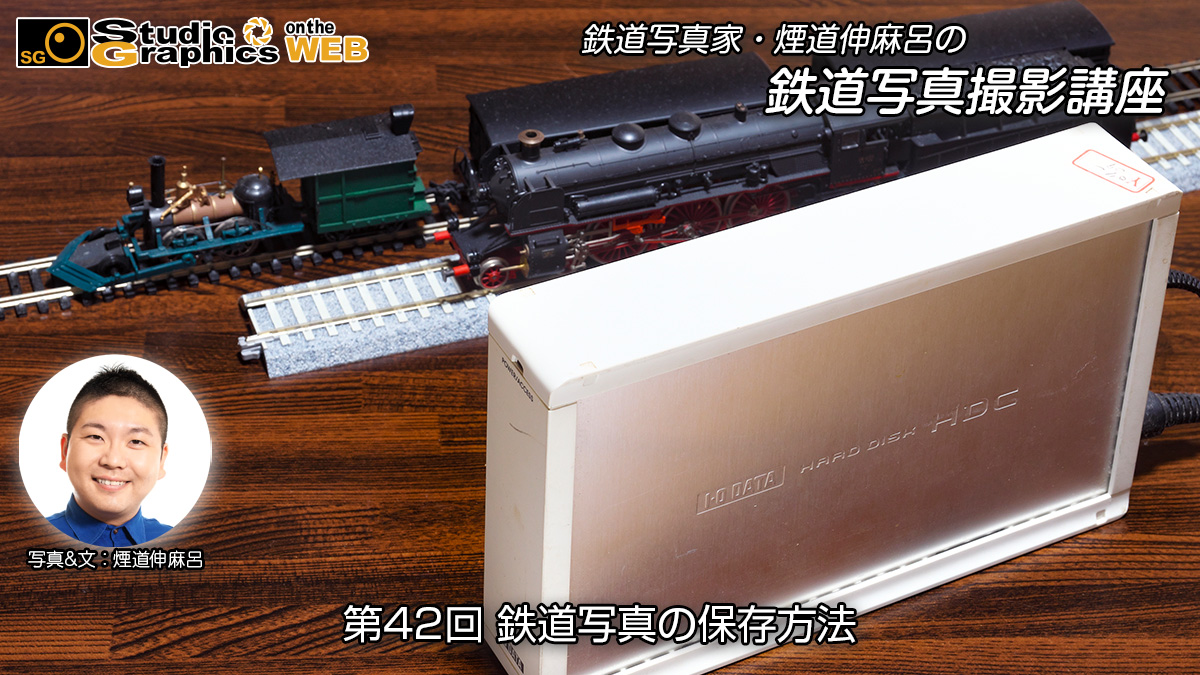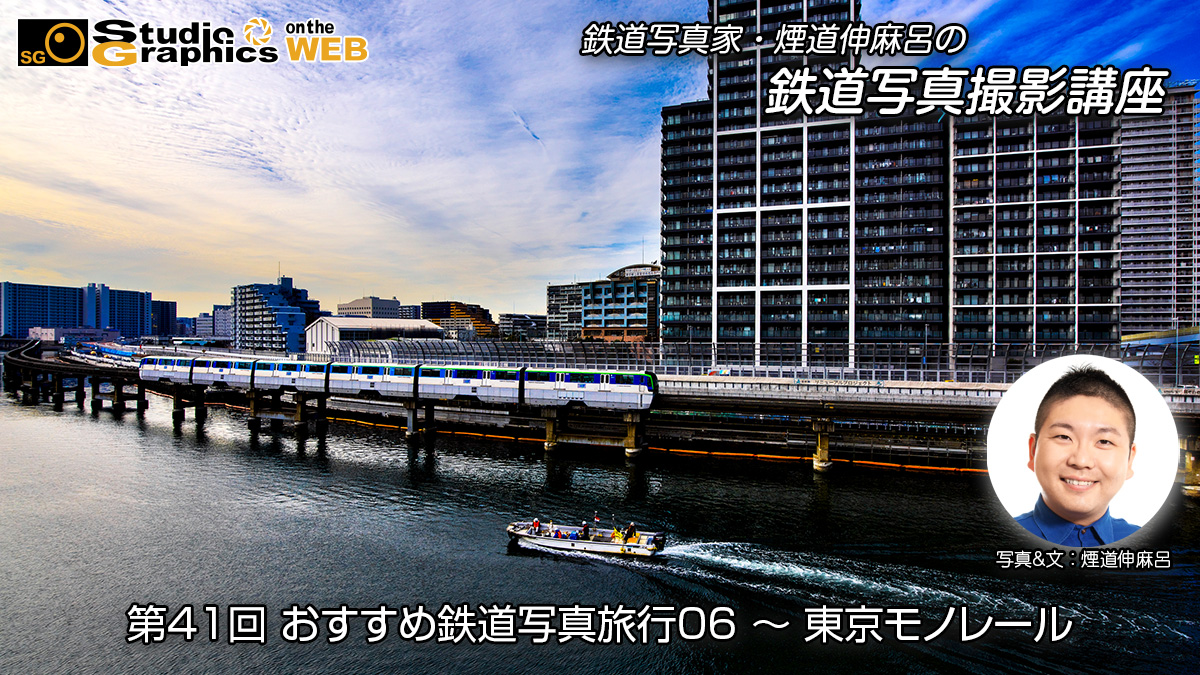鉄道写真家・遠藤真人の鉄道写真撮影講座
第17回 通勤電車の撮り方
TOPIX
| 鉄道写真の撮り方を体系的に解説している、鉄道写真家・遠藤真人の鉄道写真講座の 17 回目は通勤電車の撮り方を解説いたします。 2020年4月は外出の自粛要請が出ている都府県も多数あり、写真撮影もままならない状況下ではありますが、また外で撮影できる日を心待ちにしたいと思います。 by 編集部 |
みなさまこんにちは!鉄道写真家の遠藤真人です。鉄道写真講座にアクセスいただき、ありがとうございます。
今回は通勤電車の撮り方について解説してゆきます。通勤電車は新幹線や蒸気機関車とは違い身近な存在です。日常の中に走る列車もレンズを通してみると、また一味違った魅力に気づくかもしれません。それでは張り切ってゆきましょう!
Index
1.通勤電車の魅力

焦点距離:55mm / シャッター速度:1/800秒 / 絞り数値:F6.3 / ISO感度:200 山手線に48年ぶりに作られた、高輪ゲートウェイ駅。高層ビルをバックに走る姿は、山手線らしい風景だ。
大都市に毛細血管のように張り巡らされている鉄道網。その路線群を日々せっせと走るのが通勤電車です。特に日本の通勤電車は他国では類を見ないほどの列車本数が走っています。例えば1日の乗降客数がナンバーワンの新宿駅では、通勤ラッシュに山手線ホームに毎時 20 本以上の列車がやってきます。その数と迫力は日本の鉄道シーンならではです。
通勤電車の魅力として、各鉄道会社への直通運転も活発に行われています。一つの路線に様々な鉄道会社の列車たちがやってくるのです。それもまた通勤電車を撮影する魅力です。
2.撮影地の探し方

焦点距離:175mm / シャッター速度:1/500秒 / 絞り数値:F5.6 / ISO感度:100 2020年に新駅開業を待たずして引退したE231系電車。LED表示を写すため、やや遅めのシャッタースピードに設定した。
ここからは撮影のハウツーです。通勤電車は1両編成から、15 両編成の長さの列車まで存在しています。そのため撮影地も列車によって様々です。列車の長さによって撮影地を決めるのが良いでしょう。
短い1〜2両程度の長さであれば、横位置撮影できるポイントがおすすめです。なるべく列車に障害物がかからないような場所を見つけましょう。主に地方を走る列車などはこちらに当てはまります。
次に3〜8両程度の長さであれば、カーブか直線での撮影が良いでしょう。特にインカーブでの撮影は、車両全体のバランスもよく撮影できます。最後に9両以上の長さの列車は、直線の撮影スポットでないと全体を構図内に収めることはできません。撮りたい列車ごとに場所を選ぶことがベストです。また駅のホーム端も絶好の撮影スポットですが、近年は安全の観点から制限される場所も増えてきました。撮影者の行動が安全運行の支障とならないよう注意しましょう。
風景的に列車を狙いたい時には、高い場所からの撮影が狙い目です。俯瞰撮影といいますが、鉄道写真では展望台や山などの高い場所からの撮影です。高層ビルをすり抜ける列車や、海沿いなどを走る列車を狙うには高い場所が良いのです。普段何気なく使っている通勤電車も風景と絡めると、非日常感漂うドラマチックな写真に仕上げることがあります。高い場所からの撮影は遮るものがなく、撮りやすい場所でもあるのです。

焦点距離:78 mm / シャッター速度:1/3秒 / 絞り数値:F7.1 / ISO感度:160 新宿駅を出発した列車は、夜の街をバックに駆け抜ける。歩道橋から撮影をした。一世代前のミラーレスでは難しかった流し撮り。今ではここまでレスポンスが改善されている。
地理的な風景の他に、お花などの季節感あふれる被写体を一緒にとらえることも良いです。駅の周りには桜の木が植えられていることも多いので、比較的簡単に場所を見つけることができます。時間に余裕があれば、通勤や通学の途中にもお手軽に撮影できそうですね。
季節感といえば雪が降った日なども絶好のシャッターチャンスです。特に雪があまり降らない地域には珍しい光景となります。また別の記事でもご紹介したいと考えていますが、冬の寒い日は結露との戦いです。十分に対策をして撮影しましょう。カメラは機種やメーカーによって、動作保証できる温度が設定されています。主に0度から 40 度が一般的なカメラの範囲です。天気予報の解説などを聞いていると、地表の温度が3度以下の場合に雪となる確率が上がるそうです。これぐらいの温度となると、人間だけでなくカメラにとっても厳しい温度だと言えます。撮影の前によく確認しておきたいポイントです。
ここからは余談ですが、以前にある鉄道会社主催のフォトコンテストに選者として招かれました。応募作を拝見すると、その内容にびっくりしてしまいました。応募いただいた作品の三割が雪の日に撮影された写真だったのです。確かに雪の日は数少ないシャッターチャンスではありますが、競争率も高いシチュエーションでもあるのです。
3.通勤電車は「並び写真」も簡単
鉄道写真の中で最も難しい撮影が列車同士の離合です。列車同士のすれ違いは、鉄道ファンにとって憧れの風景の一つです。一番簡単な並びの撮影方法は、停車中に追い越しやすれ違いを撮影することです。これでも十分に価値のある写真と言えますが、鉄道ファンとしては走行中のすれ違いも撮ってみたいところです。特に都市部にある複々線区間では、比較的簡単に走行中の離合も撮影可能です。これも通勤電車らしい風景といえそうです。
この通勤電車の並び写真は、一見すると特別な光景には思われないかもしれません。しかしながら、通勤電車は置き換えのサイクルは早いです。日常と思われた光景もあっという間に過去帖入り・・・ということも少なくありません。日々変化してゆくのが、通勤電車の特徴とも言えます。何気ない普段の撮影も数年後に見直してみると貴重な資料となる場合もあります。いつでも撮れる被写体と思わずに撮影しましょう。
4.ローカル風景へと続く通勤電車
個人的な通勤電車の楽しみ方として、都市部からローカル線区間まで一本の列車で行けることも魅力の一つだと考えています。「 会社と逆方向の列車に乗ってみた 」なんて言い方をすると大げさですが、ちょっと誘惑的な表現かもしれません。私の住んでいるところでは近くに青梅線が走っています。この青梅線は立川で中央線から分離して、終点の奥多摩まで走っています。特に青梅駅から先はカーブが続く山間部を走ります。休日は新宿から奥多摩ゆきの直通列車が走っています。同じ列車に乗ったまま、これほど車窓風景にギャップがある列車も珍しいです。日常から非日常へ・・・通勤電車にはそんな魅力も詰まっています。

焦点距離:155 mm / シャッター速度:1/800秒 / 絞り数値:F 8.0/ ISO感度:160 東京アドベンチャーラインの愛称を持つ青梅線。雪の朝にはこんな絶景も現れる。通勤電車とのギャップが面白い。
5.次回予告
いかがでしたでしょうか。
以上で通勤電車における基礎知識の解説を終わります。次回は通勤電車撮影の実践編です。ご期待ください。
■ 制作・著作 ■
スタジオグラフィックス
遠藤真人